サンデー・パンチ
粂川 麻里生
実況とは何か
最近、ボクシングに限らず、テレビのスポーツ中継では音声を消して見ている人が増えているようだ。たしかに、魅力的な実況、試合の味わいをより引き出し、試合を思い出しては心の中で反芻するのに役立つような実況を聞かなくなって久しい。ましてや、ボクシングではたいていの場合、そのテレビ局に縁の深いボクサーの方に肩入れした実況になるから、試合を公正に見つめる妨げになる。最近の嵐のような問題判定の中で、しらじらしい偏向実況など聞いていられるか、という面はあるだろう。
どうして、実況がつまらなくなってしまったのだろう。僕自身、たまにCSテレビのボクシング番組の解説をさせていただくことがあるが、アナウンサーの皆さんは真面目な努力家が多い。「よくこんなことまで調べたな」と思わされるようなデータにも目を通し、コンマ何秒の単位で、どこでどんなことをしゃべろうかというのをしっかり予習してきている。視聴者は、「どうせ、アナウンサーにとってはボクシングなんてどうでもいいんだろう」という印象を受けることが多いだろうが、それは半分正しく、半分は誤解だ。たしかに、アナウンサーの多くはボクシングファンではなく、「無表情なデータ」としてのボクシングしか知らない。しかし、彼らは「実況」という仕事に対しては、実に忠実で熱心な努力家だ。ただ、その努力の方向が間違っているのではないか。
なぜ、関係諸氏の努力にも関わらず、ボクシング実況はしらけるのだろう。様々な理由が考えられるが、ボクシング中継の「プロレス化」と「ワイドショー化」というのはあげられるだろう。「プロレス化」というのは、ことさらに大げさな言葉遣いや興奮を装う声色を駆使して、いやおうなく視聴者のエキサイトメントを誘おうという手法である。これはもちろん、現在フリー司会者の古舘伊知郎氏がテレビ朝日の「ワールドプロレスリング」時代に確立した手法が広まったものである。古舘氏自身、このスタイルをF1や「筋肉〜」のような視聴者参加型「運動会」番組に応用してますますの成功をおさめた。テレビアナウンサーの歴史を変えるほどの強力なスタイルを生み出した古舘氏は天才的なアナウンサーと言っていいだろう。しかし、あの実況スタイルは、すべてのスポーツに使えるわけではなかった。
「古舘スタイル」は、表現は悪いかもしれないが「B級なもの」において、より効果を発揮する。プロレスというのは、周知(?)の通り、純然たるスポーツではない。100パーセント真剣なまなざしで見つめられてしまったら、かえって壊れてしまう類のものだ。視聴者は、そこに「出来試合」の要素が微妙に盛り込まれていることをうすうす知っており、むしろ「筋書き通り」になることを楽しむ。歌舞伎の見得を切るシーンのようなものだ。見る人たちも、「そんなご大層なものじゃない」ということは分かっており、その上で、望みうる限りのカタルシスを楽しむのではないか。別に、目の前のプロレスラーが本当に「古代格闘技パンクラツィオーン、その高貴なる魂の継承者」なんかじゃないだろうことは分かっているわけだ。ただ、そういう「お芝居」が見たいのである。レスラーが身体を鍛えるのは、試合に勝つためではなく、そういうものすごい言葉遣いをされても、視聴者があんまりしらけないようにするためである。要するに、プロレスの実況というのは「筋書き」をできるだけドラマチックに、いわば浪花節か講談、昔の映画の弁士のように語るのが仕事なのだ。だから、それは真剣な、真正なスポーツの実況とは異なり、虚構の世界で、「いかにも」なストーリーを、可能な限り派手な言葉遣いと口調で語りまくることが仕事になる。
F1やサッカーも、似たようなところがある。この2つはもちろん「プロレス」とはまったく異なり、真剣で深いスポーツだ。ただ、日本では、とりわけその導入初期においては、愛情と知識を備えたハードコアなファンよりは、ある種のファッションとしてファンになる人が多かった。そして、企業もそれに乗っかり、「ブーム」を演出する意図を持っていた。そういうところでは、プロレス同様の「虚構」が必要になる。どこかすごいのか、具体的にははっきりせず、「なんとなく、雰囲気が好き」という人を沢山巻き込まなければならないのだから。サッカー選手やレーサーたちに「○○の貴公子」、「伝説の継承者」といったプロレス式のニックネームを貼り付け、できるだけとっつきやすいストーリーを見つけ出してきて、それを大声で語り倒す。
「筋肉〜」も、そうだ。いくら優れたアスリートを連れてきても、所詮は運動会である。鍛え上げられた様々な種目の選手が、「余興」として同じ土俵で力を競うのは、たしかにそれはそれで見ごたえがあるし楽しいが、真の感動を呼ぶものではないし、見るものに生きる糧となるような思想を与えることもない。また、選手たちの肉体は、これらの余興において真価を発揮することもない。それが「B級」ということだ。こういう「B級の余興」(テレビにとってはそれは最上の素材かもしれない)を、より魅力的にするためには、「古舘式」は威力を発揮する。言ってみれば、トマトケチャップみたいなものだ。安いソーセージやフライドポテトにかけるのは美味しいが、シェフが腕を振るった「料理」には、子供だってケチャップはかけない。しかし、最近は、ボクシングに「ケチャップ」をかけることが多すぎはしないか。
また、このボクシング中継の「プロレス化」は、「ワイドショー化」とも関連している。とにかく、民放テレビの番組は、そのすべてがワイドショー化している。抜き差しならないことを報道するニュース番組でさえそうなのだ。人の生命や運命が左右されるような出来事について、「CMのあとは、最新情報です」などと平気で語れるアナウンサーは、正気とは思えない(しかも、その“最新情報”は、もう10回も見たような映像なのだ)。「オリンピック」、「世界陸上」、「世界水泳」などは、もうワイドショー化のきわみだ。そのスポーツに真に通じた人の声は遠くに聞こえるのみで、若向けのタレントや日本語もままならない女子アナウンサーがただ「感動をありがとう」とくり返す。予定調和的な「感動」だけが、このワイドショー化したスポーツテレビ番組の趣旨なのだ。9月の辰吉−アビラ戦も、文字通りのスポーツ・ワイドショーの1コーナーとして放映され、辰吉が彼とも思えない拙い試合をした挙句、レフェリーの地元びいきに救われた。あんな試合を見た後でも、ブラウン管の中のタレントたちは、訳のわからないワイドショー的コメントをはきながら、時間を消費していった(辰吉のインタビューさえ割愛しつつ……)。まさにワイドショー化されたボクシング番組、いや、スポーツワイドショーの中の「辰吉コーナー」だった。
こういった茶番は、本当にやめてもらいたい。ボクシングは、幸か不幸か、もう出来上がってしまったスポーツなのだ。その良さも、弱点も、このクラシックさにある。野球だってそうではないか。日本には、ボクシングファンをはるかに上回る数の野球ファンがおり、それぞれの深い思い入れを野球というスポーツや球団に対しもっている人が多い。テレビ局も、それをちゃんと分かっているから、表面的な盛り上げを重視することはしない。別に、「おおおおーっとぉ!」などと声を張り上げなくても、試合自体が見るものを引きずり込み、心底楽しませてくれることを知っているのだ。あるいは、あまり面白くない試合になってしまった場合、実況の力で楽しさを演出することもできっこないことも知っているのだ。
日本におけるボクシングの味われ方は、プロレスやK1はもとより、サッカーやF1よりも、野球に近いはずだ。実況アナウンスを担当する方々は、「古舘」は忘れていただきたい。「実況アナウンサーが試合を盛り上げる」という発想は、根本的に間違っていると思う。アメリカのテレビの実況を聞いてみて欲しい。絶対に、人に先んじて興奮した声を出そうなどとはしていない。盛り上げなくていいのだ。だいたい、ボクシング中継において、アナウンサーの実況のおかげで興奮することなどありえないのだから。リングや、その周辺で起こっていることを、あるいはルールや歴史の説明を、事実として伝えてもらいたい。その上で、本当に自分自身が興奮したときだけ、控えめにそれを表現していただきたい。へんてこりんな太鼓持ちや道化になるのではなく、ゲストや解説者とボクシングについて他人に聞かせる価値のある「会話」をかわしてくれるほうがいい 。
|
|
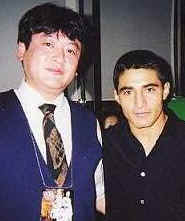
粂川麻里生(くめかわまりお)
1962年栃木県生。1988年より『ワールドボクシング』ライター。大学でドイツ語、ドイツ文学・思想史などを教えてもいる。(写真はE.モラレスと筆者)
|